メッセージ
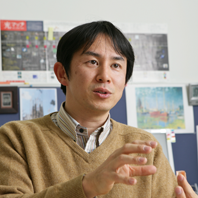 |
田中メタマテリアル研究室は、2008年4月1日に発足したナノ光学分野を専門とする研究室です。 |
|
|
立体的な3次元微細構造を直接観察できる3次元光学顕微鏡技術を基盤に,各種顕微鏡光学系や高出力レーザー、超短パルスレーザー、ナノファブリケーション技術、自己組織化現象、生体分子マニピュレ-ション技術、金属ナノ微粒子などの化学的合成手法、分光計測技術、電磁界コンピューターシミュレーション技術などを駆使しながら,ナノ微細構造が作り出す新しい光学/光技術の世界を開拓しています. 特に最近では,金属ナノ構造を利用した人工光機能材料であるプラズモニック・メタマテリアルや、3次元多層テラバイト光メモリなどがトピックスの中心です. 光技術の究極の目標は,光(フォトン)の伝播を思いのままに操るフォトン操作技術の開発です.簡単な虫眼鏡から最先端の顕微鏡や半導体製造装置に至るまで,光の伝播を操作するには,レンズやミラーを配置して,空間中に屈折率の分布を作り出すしか方法がありません.すなわち,光をどれだけ自在に操れるかは,空間中に作り出す屈折率(物質)の多様性と,それをどれだけ自由自在に3次元空間へ配置できるかによって決まります.屈折率nは,比誘電率εと比透磁率μによって構成されますが,これまでの光の世界では,物質のμはいずれも1.0であり,物質毎に異なるのはεだけです.つまり今日の光技術の世界とは,屈折率の多様性という観点からは,2つしかない物理量の片方(μ)の自由度を失った極めて窮屈な世界なのです. この問題を解決するのがメタマテリアルです.メタマテリアルは,金や銀といった貴金属をナノサイズ共振器アレイ構造に加工して作り出した人工材料です.このメタマテリアルを構成するナノ構造は人工的な原子,分子に対応し,これを使えば,物質の巨視的なεやμを物質そのものの特性とは独立して制御することができます.これは物質が決まればその光学特性も自動的に決まってしまうという従来の常識を覆し,形や構造を制御することで材料の光学特性を人工的にデザインできる新しいサイエンスと,光技術におけるブレークスルーをもたらします. 光学の教科書を開くと,分解能の限界などたくさんの理論的限界が記述されています.しかし,これらはどれも,物質のμが1.0だという前提の上で構築された光学理論から導きだされた結論であって,μ≠1.0の世界が実現できれば,これまでの限界は限界ではなくなります.実際,メタマテリアルを使った光学デバイスでは,従来の光学理論では不可能とされていた光学現象がいくつも見つかっています.私たちの研究室では,このメタマテリアル技術を駆使して,新しい光技術の世界を開き,光を思いのままに操るという夢の実現に挑戦しています. 2009年4月 田中拓男 |
||
ロゴの由来
 |
 |
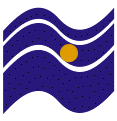 |
| 中央のメガネのようなデザインは、Metamaterialの2つの"m"の字を表すと同時に、メタマテリアルを構成するナノ共振器の形を模しています。2つの色のうち、青色は河田ナノフォトニクス研究室に敬意を表して同じ色を頂戴しました(さらに元を辿れば、この青は理化学研究所のロゴの青です)。これに新しい色として、赤色を加えました。赤と青の2つの色は、電磁気学で重要な、電気のプラスとマイナスや、磁気のN極とS極も表現しています。ロゴを囲む外枠は、金色と銀色の2色を用意しました。金と銀は、メタマテリアルもしくはプラズモニクス分野における重要な金属材料です。 | ||
Contact
〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1
Email contact[at]mets.riken.jp